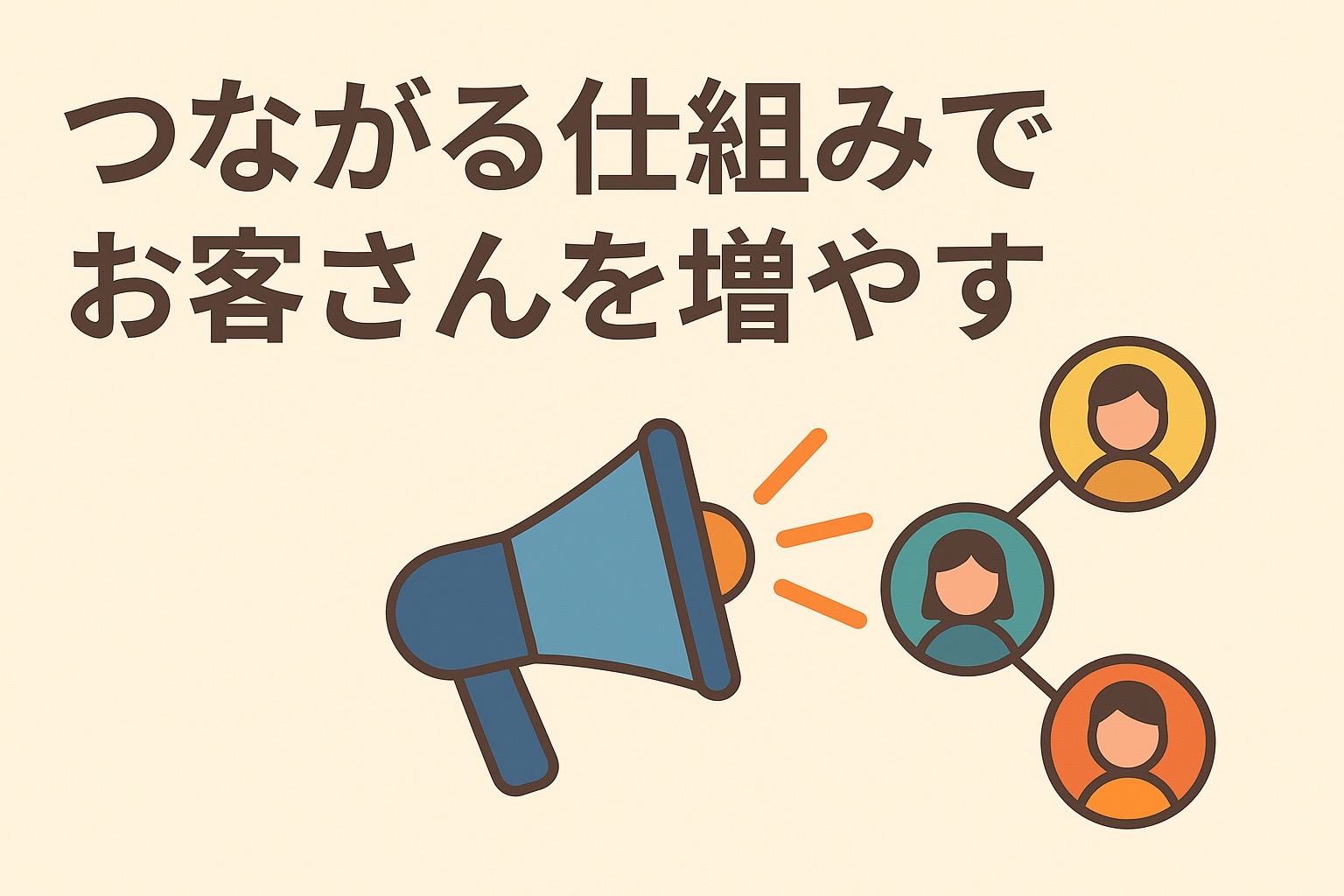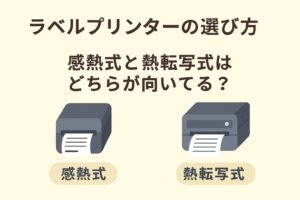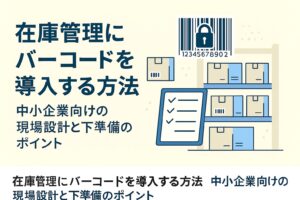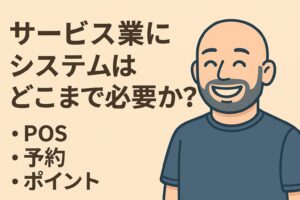商品やロケーション管理に欠かせないのが「ラベル」。
特に中小企業にとって、最小の労力で最大の成果を出すには、ラベル運用が大きなカギになります。
ラベル発行の仕組みとは?
私の現場では、FileMaker × 桜バーコードプラグインを使ってバーコードを発行しています。
商品マスター、顧客マスター、発注明細など、データベースと連携することで必要なタイミングでラベル発行が可能です。
注意点として、桜バーコードプラグインは「1アカウントにつき1端末」なので、共有環境では注意が必要です。
また、FileMakerのバージョンアップ時に更新費用が発生する可能性もあります。
ラベルサイズは統一が鉄則
ラベルサイズを複数使い分けるのは一見便利そうに見えて、実は非効率。
貼り間違い・探す・補充の手間が増えます。
私は業務全体で1サイズ(宛名ラベル)に統一し、
- 商品ラベル
- ロケーションラベル
- 顧客用宛名ラベル
すべて共通で運用しています。
ただし、商品が小さい場合には、視認性やレイアウトも加味して調整が必要です。
QRコード vs 2次元バーコードの話
以前、私のiPhoneで2次元バーコードが読み取れなくなったことがありました。
iOSのアップデートやカメラ性能の影響で、読み取れたり読めなかったりする不具合は正直怖い。
その点、QRコードはiPhoneなら確実に読み取れる。
初めてバーコード運用する企業であれば、QRコード運用からスタートするのも一つの選択肢です。
ただし、仕入商品にはQRコードが付いていないことがほとんど。
結果的には、2次元バーコードによる統一管理が最も実務的だと感じています。
ラベルは「必要なときに発行」が鉄則
よくあるのが、「ラベルをまとめて印刷して在庫化する」運用。
実際は、探す手間やラベルの貼り間違いが多発し、非効率の元になります。
ラベルは保管せず、「使うときに必要な分だけ発行」が基本ルールです。
私のFileMaker Cloudでは、これをスムーズに実現できています。
まとめ
商品ラベル運用に正解はありませんが、
- 発行の仕組み(プラグイン連携)
- サイズの統一
- 印刷ルール(都度発行)
を整えることで、業務の効率は劇的に変わります。
まずは、ラベルのサイズと出力方法から見直してみましょう。
商品管理がグッと楽になります。