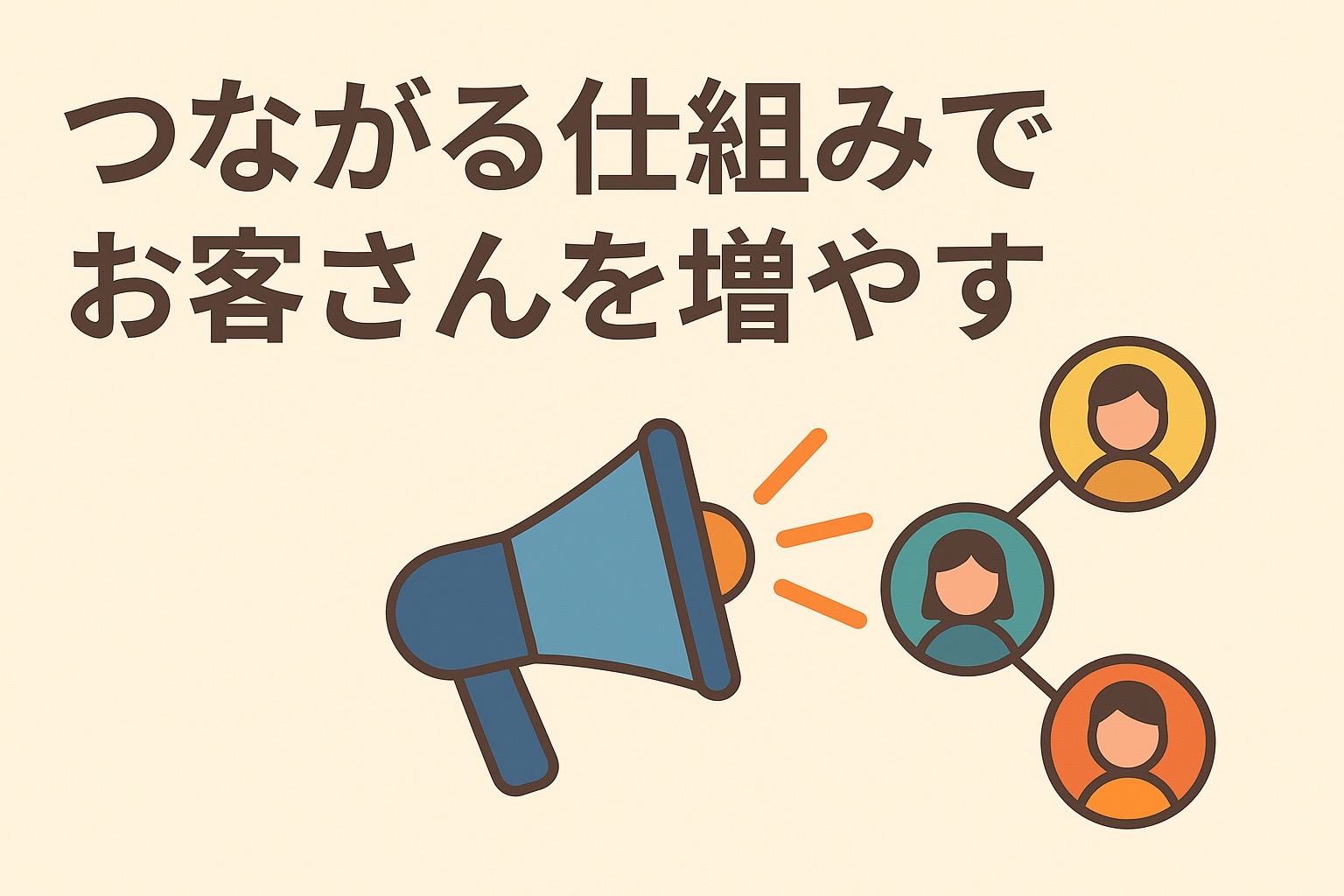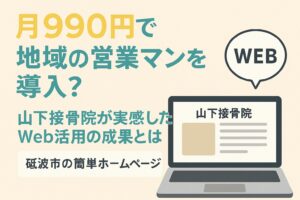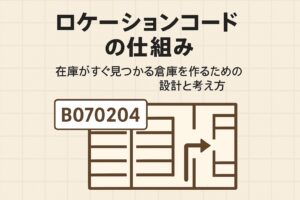はじめに
「バーコードスキャンしてるのに、なぜか出荷ミスが起きる…」
それは、検品体制の設計が不十分かもしれません。
この記事では、一次検品と二次検品の役割と違い、中小企業での現実的な運用方法についてご紹介します。
一次検品:ピッキング時にバーコードを読み取る基本体制
多くの倉庫で採用されているのが、**一次検品(ピッキング時のスキャン)**です。
- 商品を1つずつバーコードで読み取り
- ロケーションコードと照合
- カゴや箱に投入
この時点で「品番ミス・取り間違い」はある程度防げますが、数量間違いや落下、未投入などのヒューマンエラーは完全には防げません。
二次検品:梱包時に再度バーコードを読み取る方法
一部の物流会社では、梱包直前にもう一度バーコードをスキャンする「二次検品」を導入しています。
- 商品100点 → 200回スキャン
- 出荷誤送をほぼゼロに抑えられる
- スキャン漏れや箱違いも検知可能
ただし、人手と時間が2倍かかるため、中小企業では導入が難しい場合もあります。
中小企業では「一次検品の精度向上」が現実的
筆者としては、まずは一次検品を徹底することを推奨します。
二次検品がないぶん、スタッフの意識と確認力が品質を左右します。
- 商品は1点ずつバーコードをスキャン
- カゴ・箱に入れる瞬間に「声出し確認」
- 落下・置き忘れが起きやすい場所を可視化・整理
など、現場でできる工夫を積み重ねることが大切です。
検品回数と人材確保のバランス
100点の商品を扱うと、一次検品だけで100回、二次検品を加えると200回スキャン。
人材の確保や業務量を考えると、どこに重点を置くかは会社ごとに判断すべきポイントです。
まとめ:ミスをなくすのは「仕組み×意識」
完璧な検品体制には、人手・時間・設備が必要です。
しかし中小企業では、「まずは一次検品をしっかり行う」「現場の意識を高める」ことでも、十分に物流品質を向上させることができます。
自社の体制と課題にあわせて、最適な運用レベルを見極めていくことが重要です。