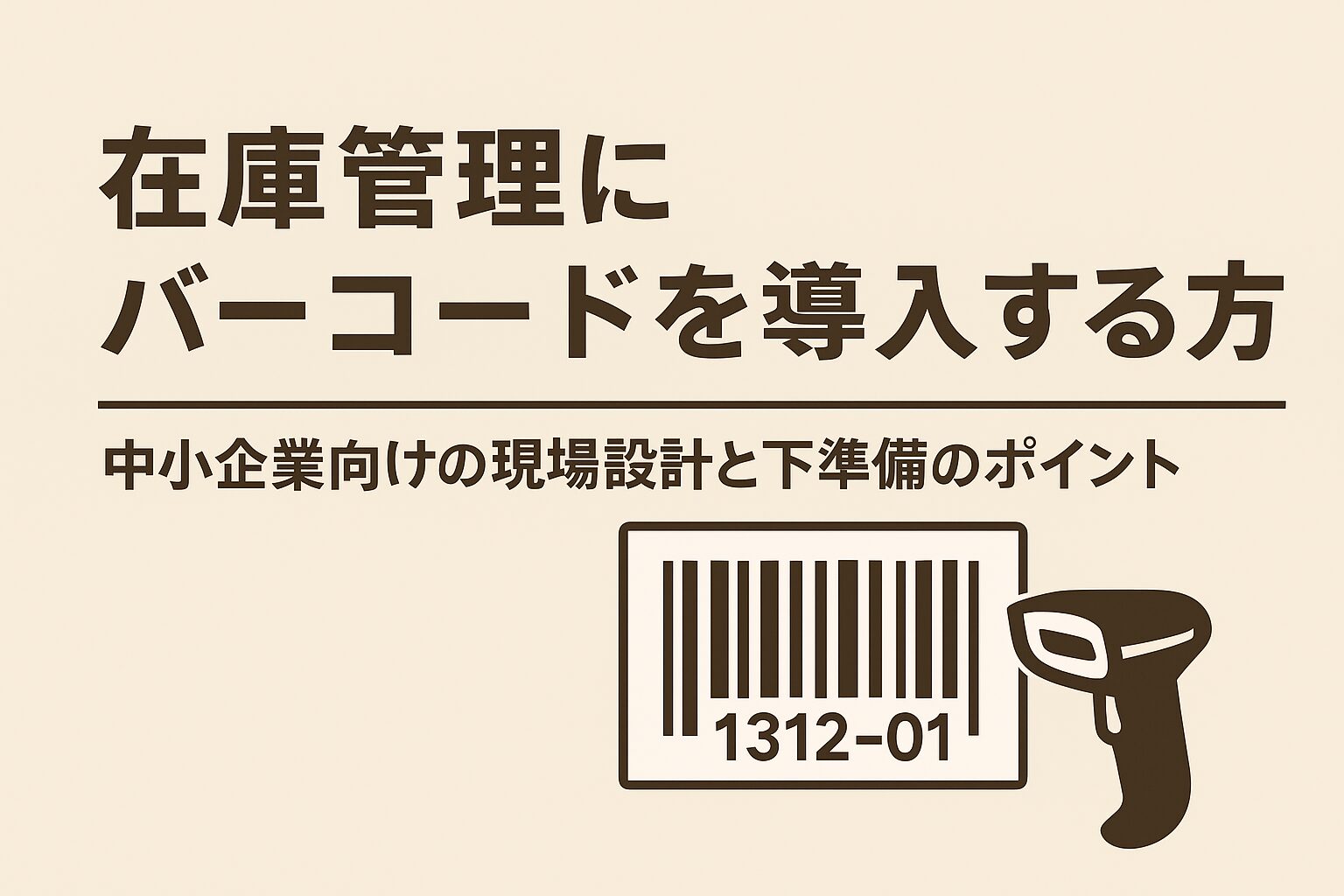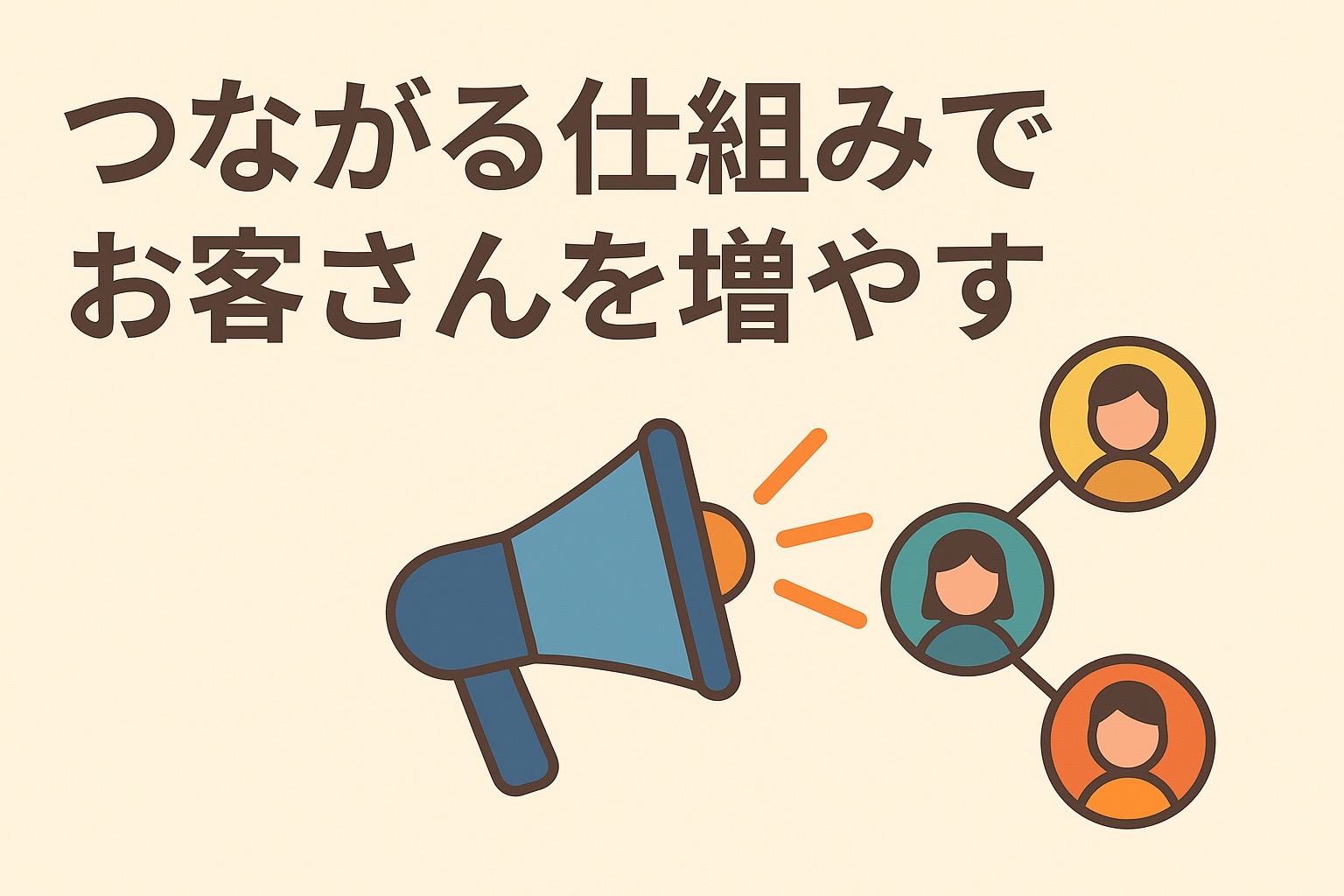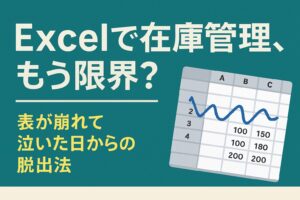「バーコード導入って、まず何から始めればいいんですか?」
僕が現場でよく聞かれる質問のひとつです。
答えはとてもシンプル。
“バーコードを貼る前に、商品コードを整えること”。
ここをすっ飛ばすと、あとで必ずつまずきます。
■ 商品コードは「覚える」ものじゃない
よく「商品番号から内容を見てわかるようにしよう」と、
アルファベット+数字で構成する工夫をしている会社もあります。
ですが、商品点数が1万点を超えてくると…はっきり言って覚えられません。
僕は**“覚えられない設計は最初からしない”**と決めています。
だからこそ、
商品コードは「加算式(連番)」で重複しないように付けていく方法をおすすめしています。
単純ですが、これが一番ミスが起きにくく、現場でも回ります。
■ コードは短く。Code39対応を意識する
バーコードは「短いほどスキャンしやすい」。
たとえばCode39を使う場合、コードが長いとラベルが大きくなり、
印字ミスや読み取りトラブルの原因になります。
だからこそ、商品コードは最小限にシンプルに。
不要な情報は持たせず、あくまで**“識別するための番号”**と割り切って設計します。
■ ECやWeb展開を見越して「-(ハイフン)」を活用
商品が色やサイズ展開している場合、コードは以下のようにします:
- 1312-01(赤)
- 1312-02(青)
- 1312-03(緑)
これによって、
- 選択肢を見える化しやすい
- CSVやECサイトで管理しやすい
- 顧客にも伝わりやすい
というメリットが出てきます。
■ 商品コードからバーコードへ ― 2つの方法
- そのまま商品コードをバーコード化する(Code39など)
- 商品コードに対して別途JANコードを割り当て、バーコード化する
中小企業では、まず①の方法から始めるのが現実的。
JANコードは年間コストや申請の手間もあるので、将来的に全国流通が視野に入ったときに検討でOKです。
■ バーコード導入の前に、まず整えることまとめ
- 商品コードは「重複しない」仕組みが命
- 加算式で自動付番できる環境をつくる
- EC連携や管理しやすさを意識して「-」などの工夫もあり
- 最後に、バーコード化する流れへとつなげる
現場で使える仕組みは、最初の準備で9割決まります。
見栄えより、**「回るかどうか」**で判断するのが現場設計の鉄則です。