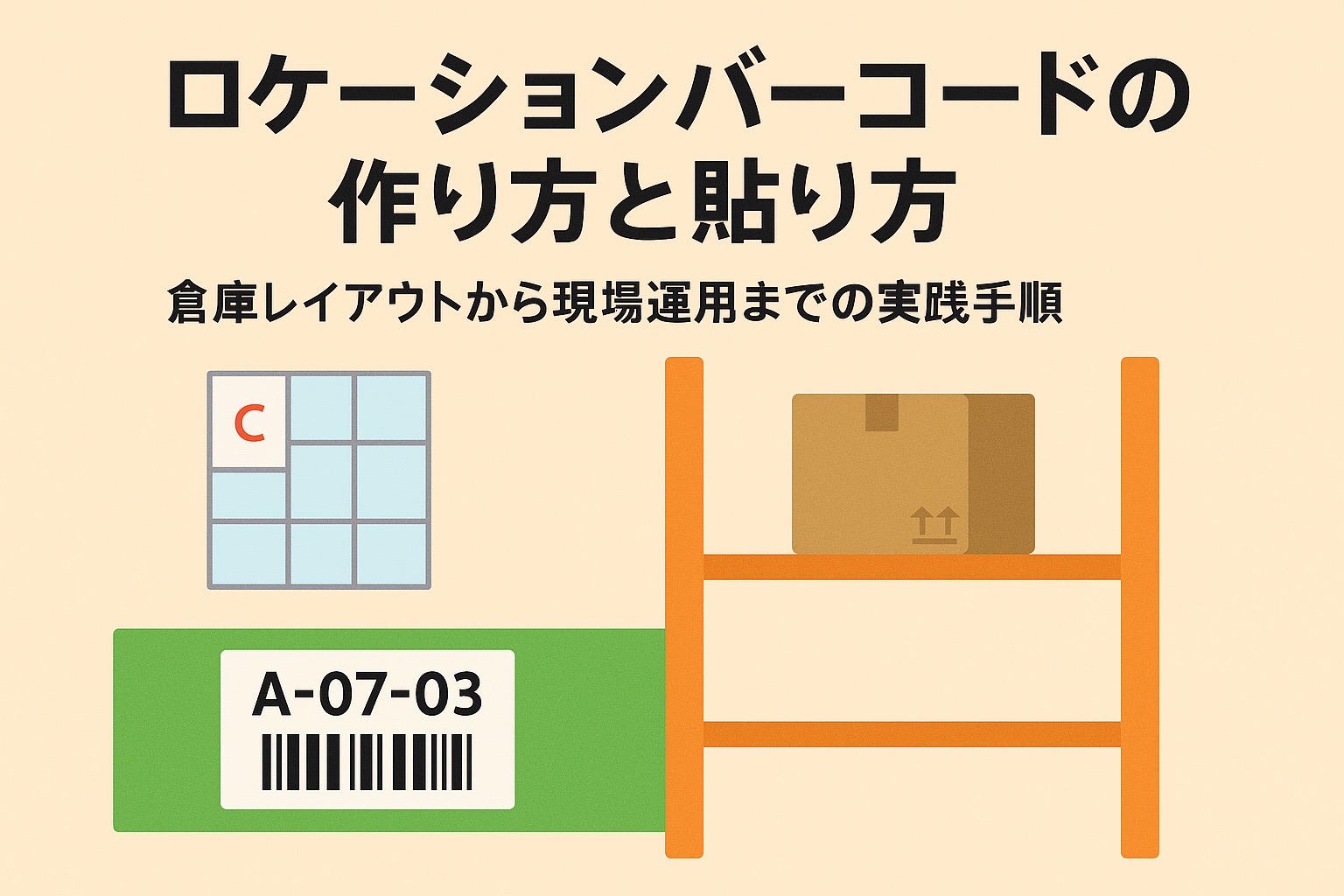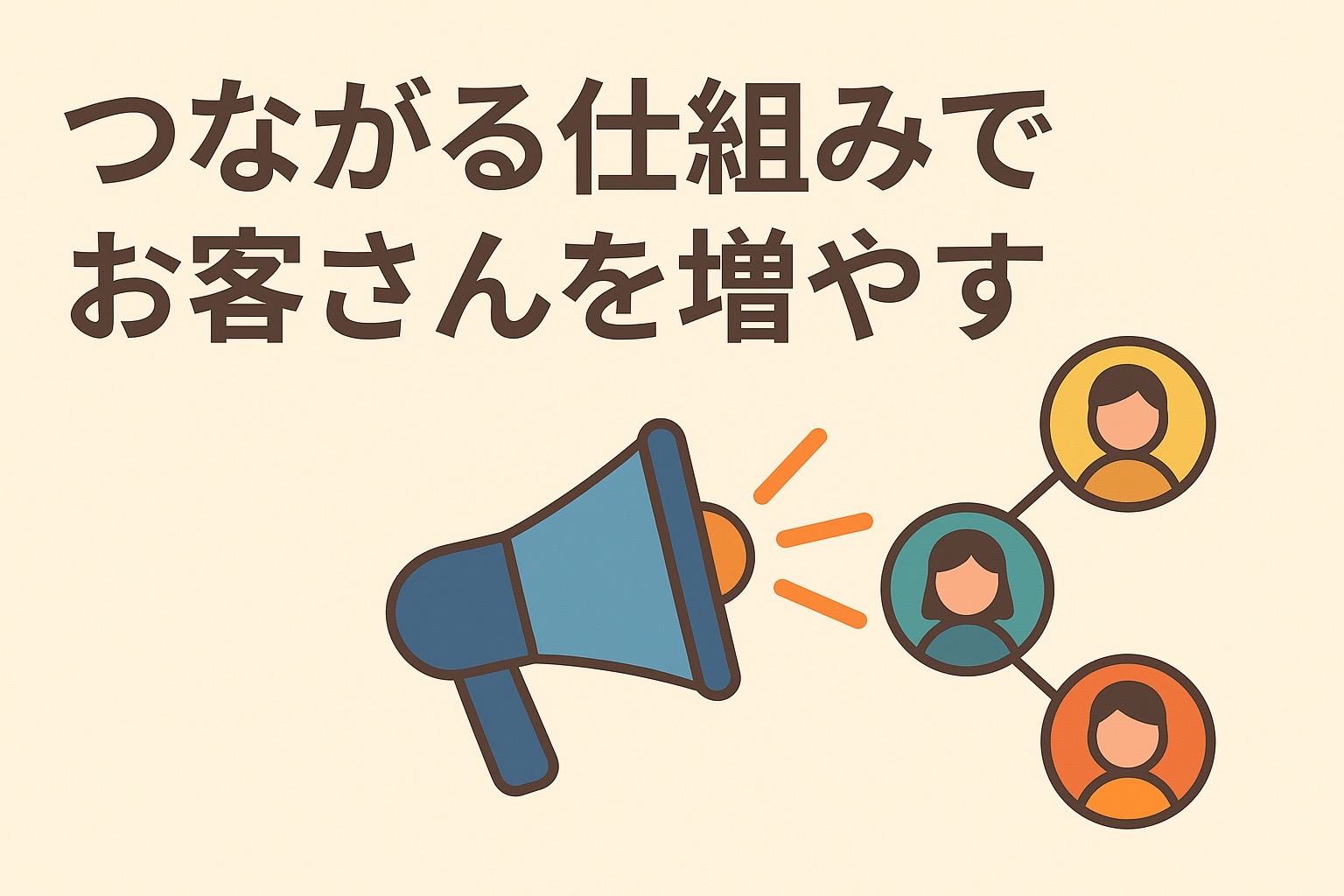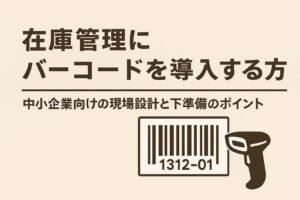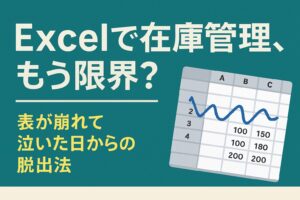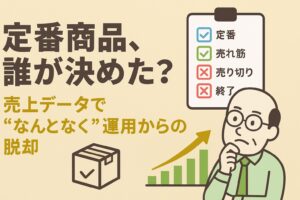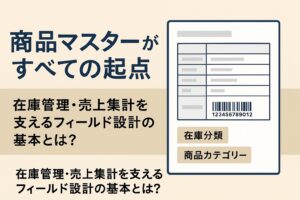「商品にバーコードを貼ったけど、保管場所がぐちゃぐちゃで探せない…」
そんな現場、見たことありませんか?
バーコード運用を本当に活かすには、ロケーションの整備が不可欠です。
■ ステップ①:まず商品すべてにバーコードを貼る
基本中の基本ですが、商品にバーコードがなければ運用が始まりません。
商品コードが整備されていれば、Code39などで即バーコード化できます。
■ ステップ②:倉庫レイアウトを設計する
- エリア(例:A・B・C)
- 棚板(例:07)
- 距離(例:03)
- 高さ(例:01)
このように、ロケーションコードを事前に設計しておきましょう。
図や地図で整理しておくと、現場での混乱が防げます。
■ ステップ③:ロケーションバーコードを一括生成する
僕のFileMaker Cloudには、
「開始〜終了」範囲を入力してロケーションコード+バーコードを一括生成する機能を搭載しています。
たとえば「Cエリア/棚7枚/列3/高さ3段」のような設計を
数秒でバーコードリストに落とし込むことができます。
6000ロケーション規模でも即対応可能です。
■ ステップ④:バーコードシールを養生テープの上に貼る
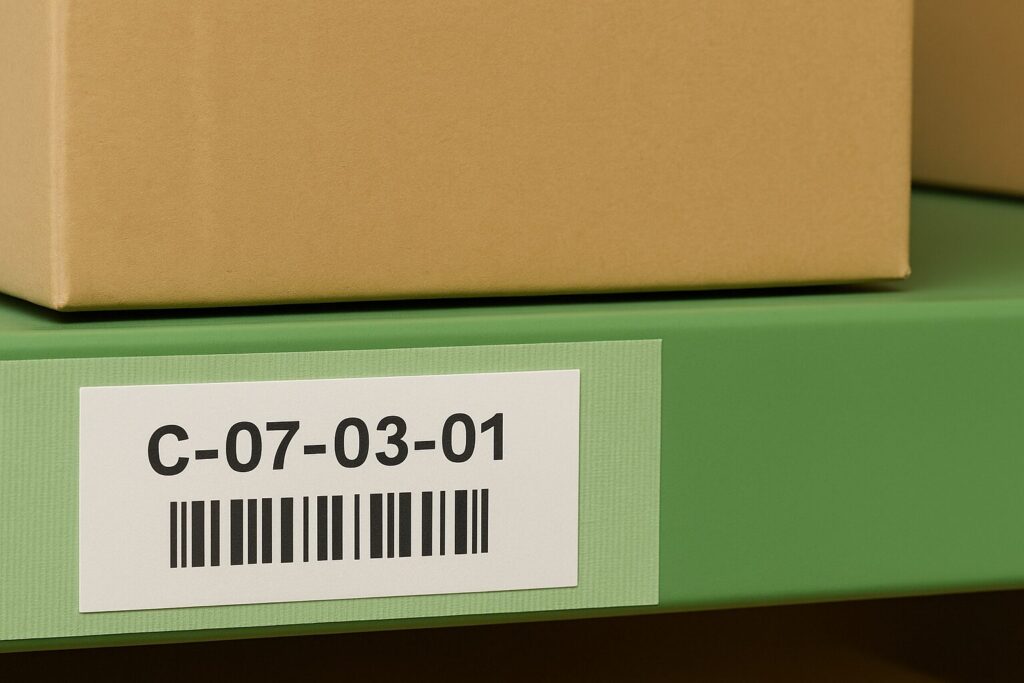
棚に直接シールを貼ってしまうと、後で剥がしたときに跡が残ったり、
棚が汚れてしまう原因になります。
そこでおすすめなのが、養生テープを下地に使う方法。
養生テープ → ロケーションバーコードの順に貼れば、
ロケーション変更や修正があるときにも簡単に対応できます。
(参考イメージ:実例写真 or イラスト画像)
■ ステップ⑤:商品をロケーションに配置し、登録する
ロケーションコードが貼り終わったら、
実際の商品をその場所に配置し、**「この棚にこの商品がある」**とシステムに登録します。
これで、入荷・出荷作業がバーコードベースで運用可能になります。
■ ステップ⑥:ピッキングロケーションとストックロケーションを使い分ける
- ピッキングロケーション:よく動く商品を置く棚
- ストックロケーション:補充用の商品を保管する棚
「ピッキング在庫が減ったら、どこから補充するか」という視点で、
ロケーション管理の仕組みを構築することが重要です。
僕は基本的にピッキングロケーション方式で運用しており、
実際の現場でも非常に効果的でした。
■ まとめ
- ロケーションの整備は“貼るだけ”ではなく“設計から始まる”
- 養生テープの活用で、柔軟な変更にも強い仕組みが作れる
- 一括生成 → シール貼付 → 商品登録 → 出荷運用へと進める
バーコードは、現場に合ったロケーション設計があってこそ、
本当に“使える武器”になります。