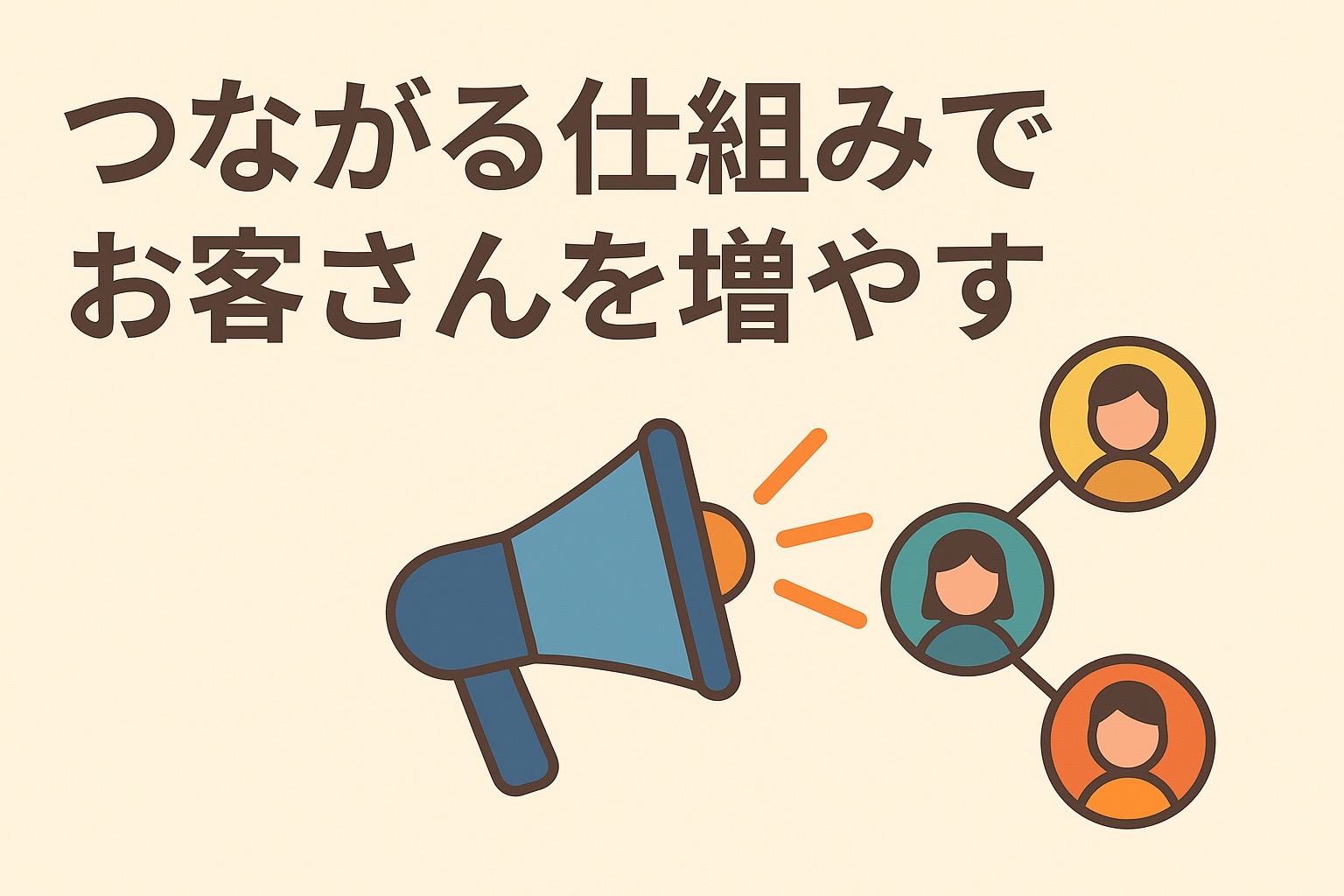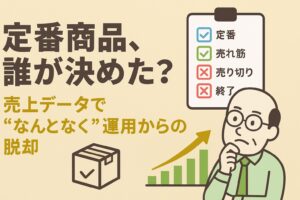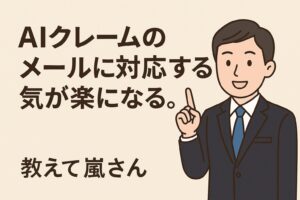目次
はじめに:「在庫が合わない…」が日常化していませんか?
「昨日までは合ってたのに、なんで?」
「多い?いや、足りない…?」
在庫差異は、現場にとって地味だけど深刻なストレスです。
しかも、差異が起きた原因が不明なことが一番の問題。
記録されていない・誰も気づいていない・でも“数が合わない”。
この記事では、現場でよくある9つの「クセ」から、
在庫差異の原因と対策を整理してみます。
よくある在庫差異の原因と現場のクセ【9選】
① 記録なしで商品を持ち出してしまう
→「ちょっと確認用に…」が記録されず、数が合わなくなる典型例。
② 誤出荷(似た品番・商品を間違える)
→ ラベルや見た目が似ていると混乱。二重チェックがないと危険。
③ 不良品の出庫漏れ
→ 「これは除外して…」と現場判断したまま記録されない。
④ 商品を違う場所に戻す
→ 「仮置き」「とりあえず」が迷子を生む。ロケーションルールが曖昧だと起こりやすい。
⑤ 入庫時の商品間違い
→ 別の商品を入庫してしまったり、JANコード違いを見落としたり。
⑥ 数量入力ミス
→ 手打ちミス、1桁ズレ、見間違い…。ヒューマンエラーは必ず起こる。
⑦ 返品入庫漏れ
→ 返品された商品を「確認中」のまま放置し、在庫に反映されない。
⑧ 入荷時点で間違っている
→ 仕入先の誤納品に気づかず、そのまま受け入れてしまうパターン。
⑨ ロケーションが定まっていない
→ 棚や保管エリアのルールがなく、「どこに戻したか分からない」状態に。
在庫差異は“人のせい”ではなく、“仕組みのせい”と考える
このような差異のほとんどは、記録とルールの不在に起因します。
人間の注意力だけに頼っていては、どこかで必ずミスが起こります。
だからこそ、「仕組みで減らす」ことがとても大切なんです。
物流のプロでも差異ゼロは難しい(でも目指している)
実際、物流専門会社の「関通」では、7PPM(100万件中7件の誤差)という業界最高水準を記録したことがあります。
- 自動化倉庫でも10PPMが限界
- アナログ現場では300PPMでも十分すごい
このレベルでも“完全ゼロ”は難しいとされる中、
私たちはまず「見直すべきクセ」に気づくことが第一歩なんです。
次に読むべきは後編:中小企業でもできる差異対策とシステム導入の現実
- 「人のせいにしない仕組みって、何から始めればいい?」
- 「高額なWMSを入れられない場合の選択肢は?」
- 「iPhoneだけでバーコード管理って現実的?」
そんな方は、次回の後編で詳しくご紹介します!
LINEで相談できます!
在庫差異、現場ルール、棚番の整備…
何から整えればいいか分からない時は、お気軽にLINEでご相談ください!